「巻藁の射が的前で出来れば良いんだけどなー」なんてセリフをよく弓道をしていると聞いたりすると思いますが、かくいう私も巻き藁の射が的前で出来ないので自分に当てはめて分析をしてみたので、みなさんの参考になれば良いなと思い、紹介したいと思います。
遠くを意識して駄目なら近くを意識して引く

当たり前のことですが、的という標的があることと、そしてその的が遠くにあることが課題だと考えられます。
そのため、近くを意識して引くことで巻き藁のように引けるようになるという一つの結論にたどり着きました。
短距離での行射実験
例えばわたしの場合で言うと的前で安土から2m程の距離で引いてみると巻き藁のように弓が引けます。
そこに的を置いたとしてもあまり変化がありません。
そこから徐々に距離を離していったときに徐々に射が崩れていきます。
昔後輩が同じことをやった時に「きっちり出来たら距離を伸ばそう」と話をしたら「射場に上陸出来ません!」と特に射場前で射が崩れていきました。
この点から距離が特に影響があると感じました。
視覚による影響
何故距離が影響を起こすかと更に考えると視覚が影響していると考えられます。
人間の情報としては目から入る情報が8割と言われるぐらいなので、そこに空間があると意識がそちらに行ってしまうと考えられます。
私自身も実体験から感じています。
例えば日本武道館は的が24個つくぐらい横に広く、天井があるのに弓道場で体験したことが無いぐらい高い4階建てアリーナです。
日本武道館で引く際は足が浮足立つぐらいの感覚におちいります。
そして、似たような感覚を感じるのが東京都小金井市にある小金井公園弓道場の遠的場です。
小金井公園弓道場はアーチェリーと併用になっていることもあり奥行きが100m程あります。
空も見えるので特に意識が空や100m以上先の安土にいってしまいうまく引けないことが多々あります。
こういったことから距離や空間をとらえようとる視覚が影響していると推察します。
視覚による影響が体にどのように起きているか理解する
わたし自身の場合、徒手でも変化が起こることに気付きました。
的前の方が手先が体から遠回りをしていました。
これはおそらく遠い距離に対して矢を飛ばそうとして無理に大きく引こうとしていたのかもしれません。
そのため体の締まるべき所も締まらず矢と肘・肩が離れていく射になっていました。
ここで一つの仮説として挙がったことが「的がある場所を意識した結果、手先で押し引きをする」ということです。
肩・肘・手先までの距離は変わらないので手先の力が肩・肘との関係を壊すほど強ければ矢と肘・肩が離れていく射になっていきます。
そのため、「如何に体の連動性が壊れないように引くか」ということを考えると意識を自分に強く置くことが必要になります。
近くを意識して弓を引く
正射必中という言葉がありますが、これは真理だと今回感じました。
精神論のように受け取られがちですが、意識の置き方としては的を得ていると思います。
自分の射が出来上がった後で狙いが付き、その先に的が有り正しく離れれば的中する。
この順番が大事なのだと感じています。
あくまで弓を引いているのであって的に何かをする訳ではないですからね。
自分の射に集中して引きたいことを実現する、その後に狙いがあるような意識を持つとうまくいく確率が上がると思います。
自分の射のほんの少しの変化が分かるように自分の射に集中しましょう。
いくら目一杯押し引きしても自分の手の長さが変わらないことを念頭に置くと働かせる力の度合いは弓の強さに合わせて決まってきますしね。
まとめ
テクニックとしては自分の引きたい射を「徒手→素引き→巻藁→的前」のように道具の有無、距離の増加によっても変わらずやりたいことが再現出来るかがチェックポイントになると思います。
的に中らないと面白くないけど的を意識すると中らないという因果なものですが、どの射撃競技でも同じことだと思うので、自分をコントロールしながら取り組んでいきたいものですね。
わたし自身も巻き藁と的前で同じように引いていると思っても実は違う部分があるから違う結果が出てしまうということを忘れないようにしたいと思います。
今回は感覚論が多くなってしまいましたが少しでも言語化したつもりなので、みなさんに少しでも伝わってくれればなと思います。
なお、読んだ方もいらっしゃると思いますが、長編のわたしのインドでの弓道記を書きましたのでご興味あればご覧頂ければ幸いです。
↓面白かったらクリックしてくれると喜びます。
にほんブログ村
ぐっちょん
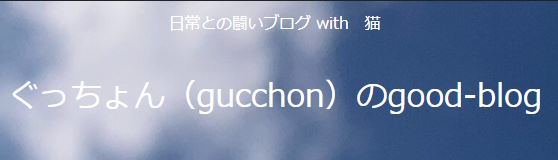




コメント
私も的前と巻藁での射の違い(特に離れ)が大きく、どうしても治らないので苦労しています。
ぐっちょんさんは、その後、この違いを克服されましたでしょうか?克服されたとすると一番の要点は何になるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
カキゾエさん
コメントありがとうございます。中々克服しきれませんが改善はしてきました。
人によって要素が違うと思いますが、巻き藁と的前の違いを明確に体で感じ巻き藁での実施事項を的前で再現するに限ります。
視覚的要素で巻き藁より的が遠くにあるため押し過ぎる。離れで弓手に意識が強く出るなどが注意事項があります。
狙いがずれている場合も離れの誤差を作り易いので確認事項です。
こういった点を注意して改善が見られました。
返信どうもありがとうございます。
自己紹介が遅れましたが、5年前に66歳で弓道を始め、現在三段の71歳です。
私の場合、巻藁と的前での一番の違いは、離れから残身にかけての馬手、肘の動きです。
巻藁では馬手がピタッと綺麗に残身で決まるのですが、的前になると、離れた後馬手が肩の線より後ろに行き、反動で肩線に戻るため、馬手が後ろに伸びたときに、そこで止まらずに最後ふわっと肩線の位置に戻る、なんともみっともない残身になってしまいます。
意識的に止めようと思ってもダメです(笑)。
巻藁ではできるのに何故かと考えるに、的前では的までのあの空間と的を意識し過ぎることにより、飛ばそうとする気持ちが働き、無意識のうちに離れで馬手を引きちぎるようにしているのだと思います。
ビデオに撮って射の比較をしても、明らかに馬手と肘の動きが違います。
おっしゃるように、巻藁での離れを体で感じることに集中したいとトライしていますが、離れは一瞬のことなので、なかなか体感して的前で再現するのが難しいですね。
カキゾエさん
返信、詳細情報ありがとうございます。
実際に射を見ている訳ではないので適当なことは言えませんので、あくまで一つの説という形でご理解ください。
巻き藁よりも的前は標的が遠く、下に見えるという点があります。
例えば遠く見えるから妻手を大きく引き抜いてします、下にあるから下を狙い過ぎて引き抜いてします。
巻き藁と的前の感覚を確認するのと同時に狙いも一つの要素として考えられます。
徒手から実際の離れの動きをゆっくり再現してみてそれを同様に巻き藁、的前で再現するのも良いと思います。
理解出来ているようで理解出来ていない動きがあるかもしれません。
自分の体は自分がよくわかっているはずですが、制御が難しいですよね。
返信ありがとうございます。
お考えの説、確かにその通りではないかと思います。
巻き藁の射での離れの感覚を、そのまま的前でできるよう、ゆっくりとその感覚を覚えて体に沁み込ませ、的前で再現できるよう精進します。
今日も道場で引きましたが、少しずつ改善されてきているように感じます。
ありがとうございました。